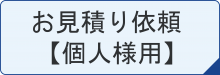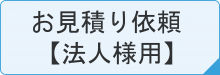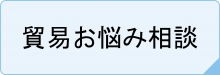公開日:2020/12/21 /

1.事前確認
✍輸出可能地域の確認
和牛はどの国にも輸出できるわけではなく、2国間協議を経て、条件を確立した国にのみ輸出が可能です。
輸出条件は国によって違いますので、輸出したい国の条件を確認し、それを満たさなくてはなりません。
✍輸出食肉取り扱い施設の確認
和牛は認定を受けた食肉処理工場(と蓄場)で処理されたもののみ輸出ができます。
認定と蓄場は輸出国ごとによって違いますので注意が必要です。
和牛の銘柄を指定して輸出したくても、その銘柄を取扱っていると蓄場が輸出国の認定リストに含まれていない場合、輸出できません。
2.必要書類
一連の手続きに必要な書類は次のとおりです。
| 書類名 | 書類作成者等 |
|---|---|
| インボイス | 輸出者が作成。 |
| パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
| 原産地証明書 | 商工会議所にて取得。パッキングリストを商工会議所に提出。(※) |
| 部位明細書 | 食肉処理工場が作成。 |
| 衛生証明書 | 食肉処理工場が作成。 |
| AIR WAYBILL | 航空輸送の場合、フォワダー(通関会社)が発行。AWBとも言う。 |
| SEA WAYBILL | 海上輸送の場合、フォワダー(通関会社)が発行。 |
| 輸出検疫証明書 | 動物検疫検査終了後に農水省より発行。 |
※アクセス・ジャパンにて代行取得が可能です。
3.動物検疫検査
✍動物検疫申請に必要な書類
動物検疫検査に必要な書類は次のとおりです。
| 書類名 | 書類作成者等 |
|---|---|
| インボイス | 輸出者が作成。 |
| パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
| 原産地証明書 | 商工会議所にて取得。パッキングリストを商工会議所に提出。(※) |
| 部位明細書 | 食肉処理工場が作成。 |
| 衛生証明書 | 食肉処理工場が作成。 |
※アクセス・ジャパンにて代行取得が可能です。
✍動物検疫申請
上記の書類をもとに通関業者が申請書を作成し、書類に矛盾が無いかを確認します。
申請書に必要書類を添付して、農水省の動物検疫所へ提出します。
✍動物検疫検査の実施
検査官立会いの下、現物(和牛)及び現物に貼ってあるラベルの内容(部位名・数量・重量等)と書類が一致しているかを確認します。
✍輸出検疫証明書の発行
現物と書類に問題が無ければ《輸出検疫証明書》が発行されます。
4.輸出通関
✍輸出通関に必要な書類
輸出通関に必要な書類は次のとおりです。
| 書類名 | 書類作成者等 |
|---|---|
| インボイス | 輸出者が作成。 |
| パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
| 原産地証明書 | 商工会議所にて取得。パッキングリストを商工会議所に提出。(※) |
| AIR WAYBILL | 航空輸送の場合、フォワダー(通関会社)が発行。AWBとも言う。 |
| SEA WAYBILL | 海上輸送の場合、フォワダー(通関会社)が発行。 |
| 輸出検疫証明書 | 動物検疫検査終了後に農水省より発行。 |
✍輸出通関書類の作成
上記の書類をもとに《輸出通関申告書》を作成します。
✍税関へ申告
《輸出通関申告書》に必要書類を添付して税関に申告します。
審査が完了し、問題が無ければ《輸出申告許可書》が発行されます。
以上で手続きは完了です。
必要書類と商品(和牛)を飛行機、もしくは船で輸出国へ運びます。


5.おまけ
✍牛肉の輸出梱包について
海上輸送であればリーファーコンテナを使用することで、鮮度を維持することができますが、20FEETコンテナにするにしてもそれなりの物量が必要です。
※LCLの保冷の輸送は航路が限られておりますので、お問い合わせくださいませ。
コンテナを仕立てるのに満たない物量の場合、航空便が使用されます。
飛行機内の温度は常温のため、そのまま搭載すると鮮度が落ちてしまいます。
そこで鮮度維持の手法として下記の2つがあります。
❏保冷のトライオールで商品を囲み、ドライアイスを入れて保冷をする。
👉メリットはなんと言っても鮮度が維持されることです。
👉デメリットはトライオールの費用が掛かることです。
※トライオールとは1m x 1mの強化段ボールで、保冷の場合は内側に発泡スチロール板を付けます。非常に高価。
❏フライトを直行便にし、出発ギリギリまで冷蔵庫保管。飛行機内では常温になってしまいますが、到着空港ですぐに冷蔵庫に入れる。
👉メリットはコストが安いことです。
👉デメリットは常温でどれくらいの時間品質が維持できるのか見極めるのが困難です。
※牛肉は真空パックされていることが多いため、品質が落ちにくい状態となっております。
✍輸出する牛の月齢について
月齢30ヵ月以下を条件としている国があります。
これはBSE(牛の病気)のリスク回避のために設定された条件です。
牛は月齢を重ねることで、病気などのリスクが高まる一方、長期肥育による品質の向上が見込まれます。
日本に多くあるブランド牛は、名乗る条件の一つに長期肥育があります。
生産者としては長期肥育し付加価値を付けてブランド牛として出荷したいところですが、各国の月齢30ヵ月以下という輸入条件が壁となっていました。
そんな中、農林水産省が各国と交渉した結果、月齢条件を撤廃する国が多くなってきています。
一例ですが、令和2年6月2日にマカオ向け牛肉輸出が月齢撤廃となりました。
日本の誇るブランド牛が、ますます世界に広がることでしょう。
お問い合わせはこちら
些細なことでも構いません。
お気軽にお問い合わせください。